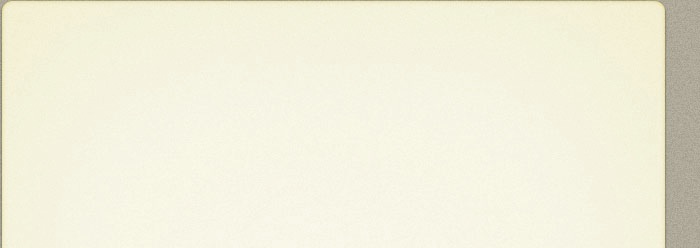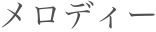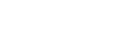「ねぇ。私の物語をいつか書いて欲しいなぁ。」
妖精は、少女に言った。少女は、笑って答えた。
「いつか必ず書くわ。あなたの事を素敵な物語にして、たくさんの人達に
読んでもらうの。」
二人は、森の奥の秘密の花畑でそう約束をした。
おっと、突然、物語が始まってしまったけれど、この物語は決して夢物語なんかじゃないんだ。誰でも昔は、少しだけでも見た事がある。そんな儚くも純粋な物語なんだ。
少女は、家の裏に広がる森で遊ぶのが大好きだった。その森には、少女が誰にも教えない花畑があって、少女はそこで遊ぶ事が何よりも好きで、幸せだと思っていた。
そんな少女が、不思議な体験をしたのは6歳の時だった。花畑に寝転がって花の香りを楽しんでいると、どこからか声が聞こえた。少女は、辺りを見渡したけれど誰もいなかった。
「ここよ。こっちこっち!!」
少女が、声のする方を一生懸命に探すと、草の陰に小さな女の子が立っていた。少女は、人形かしらと思った。
「そんな顔で見ないでよ。私、メロディーって言うの。あなたは?」
少女は、目の前で起きている事が信じられなかった。何度も目を擦ってみる。しかし、目の前で彼女は消える事なく、じっと楽しそうに微笑んで少女を見ていた。少女は、震える声で答えた。
「私は、綺羅よ。」
「ふ〜ん。キラかぁ。良い名前ね。」
「あなたも素敵なお名前ね。」
「でしょう。とっても気に入ってるんだ。私はね。歌を歌うのが大好き
なの。あなたは?」
「私は、ここで寝転がって色々な事を考えるのが好き。」
「色々な事って?」
「そうねぇ。例えばあの雲は、どこから来てどこへ行くんだろうと
か・・・ここに咲いている花の種は誰が連れてきたんだろうとか・・・
まぁ、そんな所かな。」
「へぇー。素敵ね。ねぇ。私とお友達になってくれないかな?」
「おともだち?」
「そう。お友達。一緒に歌を歌ったり、色々な話をしたり、遊んだりする
の。考えただけでも楽しくなっちゃうな。」
「良いわよ。」
こうして二人は、この秘密の花畑で遊ぶようになった。
メロディーは、10センチ位の小さな女の子で、その背中にはトンボのような透明の羽根があった。初めて綺羅がメロディーに出会った時、彼女は服も着ていなかった。無垢な存在だったと言えば聞こえは良いけれど、ただ単に裸だったんだ。出会った次の日、綺羅はメロディーに、自分のお人形が着ていた服をプレゼントした。メロディーには、サイズが大きかったけれど、彼女はそのプレゼントをとても喜んだ。その服は、雪のように白い、綺麗でシンプルな細身のドレスだった。そして、そのドレスは、メロディーにとても良く似合っていた。
綺羅は言った。
「私のお人形が着ているよりも、あなたが着ている方がずっと素敵だわ。」
メロディーは、草の上をくるくると回ってみせた。彼女が、そのドレスをとても気に入っているのが言葉に出さなくても分かった。
メロディーは言った。
「何かお礼をしなくちゃね。何が良いかしら?」
「別に良いよ。気にしなくて・・・・・」
綺羅は、メロディーに言った。
彼女達は、それから毎日のように、森の秘密の花畑で会い、遊んだり、話をしたりした。4つの季節が2回流れて、綺羅は8歳になった。
ある日、綺羅は、メロディーに言った。
「ねぇ。私のお家に来ない? 私のお家で一緒に暮らさない?
ねぇ? これって名案だと思わない。」
綺羅は、とっても楽しそうに言ったが、メロディーは、少し困った顔をして綺羅を見つめると、
「それは、無理かなぁ・・・・・ 私は、この森の外には出られないんだ。
ここが好きだし、ここを守る為に私は存在しているの。
素敵な話だけど・・・・・」
「ううん。ごめんね。気にしないで!!私もここが好きだし、毎日来るから
良いのよ。私こそ勝手な事を言って、ごめんね・・・ そうだ!友達が、
お人形で遊ばなくなったからってたくさん服をくれたの。とっても可愛い
洋服がいっぱいなんだよ! きっと、メロディーにとっても似合うよ。」
「えぇー!? やったー。本当だ!とっても可愛いねぇ・・・・・。」
メロディーは、とっても嬉しそうに洋服を手に取っては綺羅の顔を覗き込んで似合うかどうか聞きながら、自分に合わせてみせた。一通りの洋服を合わせ終わるとメロディーは、綺羅に聞いた。
「友達かぁ・・・良いわね。綺羅にはお友達がいっぱいいるの?」
「えっ?そうだなぁ・・・小さい町だからねぇ。そんなに沢山はいないよ。
それに仲の良い友達はみんな家が遠いからねぇ。なかなか遊べないし
ねぇ・・・・・」
「ふ〜ん。そうなんだ・・・・・私の事を話したりするの・・・・・?」
「ううん。話さないよ。だってここは私だけの秘密の場所だから・・・。
誰にも話した事ないもの。」
「そうかぁ。良かったぁ。」
「どうして?」
「ううん。何でもないよ。ただ聞いてみただけ。」
「へんなのぉ。」
それから、時が流れ、季節は繰り返し過ぎ去って行き、綺羅は10歳になった。綺羅は、秘密の花畑に行く事が少なくなってきていた。そして、綺羅は、物語を作るようになった。彼女が、ずっと頭の中で考えて、想像していた世界が物語という形になって世に出てきたのだ。綺羅は、秘密の花畑に寝転がって、ノートに物語を綴っていった。メロディーは、ノートの上に寝転がって、鼻歌を歌いながら、それを楽しそうに見ている。綺羅は、物語が出来ると、それをメロディーに話して聞かせた。はじめは、短く、つたない文章だったその物語は、メロディーに話す事によって不思議な程に綺麗な物語へと変わっていった。そして、メロディーは、綺羅の話す物語が大好きだった。
「綺羅の作る物語って、とても素敵ね。私、綺羅の作る物語が大好き!!」
メロディーは、綺羅の作り出す物語に、ある時は喜び、ある時は泪を流し、ある時は笑い、ある時は笑い、ある時は怒った。メロディーは、綺羅の作り出す物語の最初の聞き手であり、理解者であり、相談相手だった。秘密の花畑で作られた物語が50話を過ぎた頃、綺羅は12歳の誕生日を迎えていた。綺羅は、どんどんと成長していったが、メロディは最初に出会った頃と少しも変わる事がなかった。いつまでも、あの最初に出会った頃の笑顔のままだったのだ。メロディーは、新しい物語が出来ていない時は、何度も以前に作られたお気に入りの物語を綺羅に話してとせがんだ。綺羅は、物語を作る合間に、メロディーに話をして聞かせた。メロディーは、綺羅の声に耳を傾けながら、本当に楽しそうに微笑んだ。幸せを感じていたのだ。綺羅の作り出す物語で、メロディーの心はいつも満たされていた。
少女は、13歳になり、進学をし、隣町の学校まで通うようになった。秘密の花畑に行くのは、休日だけになってしまった。物語も少しずつしか作る事が出来なくなってしまった。週末に花畑に行くとメロディーは、待ってましたとばかりに、綺羅に話をしてとせがんだ。綺羅は、微笑みながらせがむメロディーに、言葉を選ぶように話して聞かせた。メロディーは、綺羅に会えなかった間に何があったのかを、綺羅に話した。メロディーの生活は、森の中だけの筈なのに、その話は壮大な物語のようだった。森の動物達や、虫達、鳥達、草花や木々の話。妖精であるメロディーは、色々なものと話をする事が出来たのだ。綺羅の作る物語にメロディーの話が、強い影響を与えた事は言うまでもないだろう。
あっという間に時は流れ、綺羅は15歳になり恋をした。多分、遅過ぎる恋だろう。空想と物語の世界に身を置いていた彼女にとって、現実の世界での本当の意味での恋は、無縁の世界のものだった。彼女は、抑えられないその感情で、胸が張り裂けそうになるのを感じていた。ある日、綺羅は、メロディーにそんな想いを話した。メロディーは、綺羅の話す声に静かに耳を傾けていた。話が終わるとメロディーは綺羅に言った。
「私には分からないなぁ? どんな気持ちなんだろう?」
綺羅は、メロディーの為に、その想いを綴った物語を書いた。綺羅が綴った言葉は、輝きを持ち、その物語は、今まで作ったどの物語よりも綺麗な言葉と優しさと美しさを持った物語となった。メロディーは、彼女の作ったその物語を聞いて微笑み、そして言った。
「とても素敵な物語ね。私、この物語が好きだわ。綺羅そのものって感じが
する。今まで聞いたどの話よりも、私は好きだな。」
メロディーは、そう言って微笑み、そして泪を流した。
「どうして泣くの?」
「分からない。」
綺羅は、少年と愛を育むようになった。恋は、いつしか愛に変わっていった。そして綺羅は、物語を作らなくなってしまった。メロディーのいる花畑にも行かなくなってしまった。少年の名は、「純」。純は、心の優しい綺羅にぴったりの男の子だった。綺羅は、純と一緒にいる時間を大切にするようになった。物語は、時間を止めてしまったのだ。
時が流れた。それは、綺羅にとっては、とても短い時間で、メロディーにとっては、長い時間だった。ある夜、綺羅は、メロディーの夢を見た。夢の中で、メロディーは、手を振った。メロディーの顔は、泪でぐしゃぐしゃになっていた。綺羅は、目を覚ますと明け方のまだ薄暗い森の中を走った。そして、花畑に着くとメロディーを探した。
「メロディー! メロディー!!」
綺羅は、必死に大声でメロディーの名を呼んだ。草の下を、木の上を、花の陰を綺羅は、必死にメロディーを探した。泪が流れて止まらなかった。綺羅は、大切な何かを失くしてしまった気がした。綺羅は、花畑に倒れ込んで泣いた。溢れる泪が、零れては、地面に吸い込まれていった。
「どうしたの? こんなに早く?」
綺羅は、声のする方に振り返った。泪でぼやけた視界の先に、メロディーの笑顔があった。メロディーは、綺羅の顔を覗き込むと不思議そうに言った。
「どうしたの? なんで泣いているの? 何かあったの? ねぇねぇ?」
綺羅は言った。
「あなたが泣いている夢を見たの。私は、あなたがいなくなってしまうと
思ったわ。そう思ったら、悲しくて仕方なくなって・・・・・」
メロディーは、綺羅に言った。
「どうして? 私は、消えたりしないわ。あなたが私を覚えていてくれる限
りは・・・・・・ だってそうでしょう? 違うかな? さぁ、泪を拭い
て!!」
綺羅は、泪を拭くとメロディーを掌に乗せて胸を寄せると強く抱き締めた。メロディーが慌てて声を上げた。
「つぶれちゃうー。苦しいよー。綺羅! 綺羅ってばぁー!!」
綺羅は、メロディーを地面に降ろすと胸に手を当てて言った。
「メロディーの感触がここにあるわ。」
「へんなのぉー。」
メロディーは、けらけら笑った。
「ねぇ。綺羅・・・・・。」
「なあに?」
「いつか私の物語を書いて欲しいなぁ。」
綺羅は、メロディーに笑って答えた。
「いつか必ず書くわ。あなたの事を素敵な物語にして、沢山の人に読んでも
らうの。」
二人は、森の奥の秘密の花畑で、そう約束をした。
綺羅は、また花畑に行くようになった。
そして前と同じように、メロディーに物語を作って話して聞かせるようになった。綺羅は、メロディーとの時間を過ごす事によって、自分が物語を作る事が心から好きなんだと再認識した。綺羅は、純と過ごす時間と同じ位にメロディーと過ごす時間が大切だという事を心で感じていた。
ある日、純が綺羅に聞いた。
「このノートは何?」
「物語を書いてるの。もうこのノートで17冊目よ。」
「へぇー。知らなかった。読んでも良い?」
「どうぞ。でも面白くないかもしれないわよ。」
純は、ノートを手に取ると真剣な顔で彼女の綴った物語を読み始めた。彼が、ページを捲る度に綺羅は、胸の鼓動が高まるのを感じていた。純は、一つの物語を読み終えると綺羅の顔を見て言った。
「すごいね。何か上手く言えないけど好きだな。こういう物語。」
「本当? 本当にそう思う?」
「えっ?どうして?本当だよ。嘘付いてもしょうがないじゃない。文章とか
は、少し直した方が良い所もあるかもしれないけど、僕は好きだよ。
ねぇ、他のも読んでみたいな。今度、貸してね。」
「嬉しいなぁ。とても嬉しい。是非、読んでね。」
こうして、純は、綺羅の作った物語を全て知る、この世で2番目の存在になった。純は、綺羅の物語を読むと、事細かく感想を伝えた。純は、特に文章に長けていた訳ではなかったが、彼の感想は、綺羅の物語に深みを与える事になった。純は、綺羅の作る物語を通して、綺羅の心の奥底に触れているような気がしていた。
「すごい才能だね。尊敬するよ。綺羅の綺麗な心が形になったみたいだね。
こんな才能があったなんて少しも知らなかったよ。僕達、付き合い初めて
2年も経つのに、本当は知らない事がいっぱいなのかもしれないね。綺羅
の事は、全て知っていたいな。」
「今ね。友達の事を物語にしているの。とても長い話になりそうだわ。彼女
の事を書くって約束したのよ。」
「へぇー。彼女って誰?」
「きっと信じられないわ。話をしても・・・・・そうだ。今度会って欲しい
な。私の大切な友達なの。」
「ふ〜ん。そうなんだ。良く解らないけど、素敵な友達なんだね。きっと
・・・・・う〜ん、やっぱり知らない事がまだいっぱいだ!!」
純は、不思議そうに、そして嬉しそうに言った。
綺羅が、純を連れて秘密の花畑に行ったのは、それから少し経った週末だった。それは、秘密の花畑が、ただの花畑に変わってしまう事だという事に、この時、綺羅はまだ気付いていなかった。二人は、森の中を花畑に向かって歩いて行った。花畑には、いつもと同じように綺麗な花が咲き、その花達が出す香りに包まれていた。綺羅は、辺りを見渡すとメロディーを呼んだ。
「メロディー! メロディー!!」
返事が無い。綺羅の声は、空高く吸い込まれていった。
「おかしいなぁ? どうしちゃったのかしら・・・・・」
「どうしたの? ねぇ? 友達ってここで待ち合わせしているの?」
純は、不思議そうに綺羅の顔を見つめている。
綺羅は、何度もメロディーの名を呼んだが、メロディーが姿を現す事は無かった。綺羅は、いつかメロディーとした話を思い出していた。急に泪が頬を伝った。メロディーの声が綺羅の脳に駆け巡った。
「秘密の花畑」
「誰にも話していない。」
「良かった!!」
綺羅は、自分のしてしまった過ちに気付いた。泪が溢れて止まらなくなった。純は、綺羅の泪を見て一瞬驚いたが、綺羅の泪を拭うと話し始めた。
「どうしたの? ここに大切な友達がいるんでしょう? どうして泣いてい
るの?」
綺羅は、純に全てを話した。花畑に並んで座り、物語を話すように言葉を綴っていった。綺羅は、純に笑われると思っていた。純は、信じてくれないと思った。いや信じられる訳が無いとさえ思った。
ところが純は、笑わなかった。じっと黙ったまま、綺羅の声に耳を傾けていた。綺羅が、話し終えると純は綺羅の顔をじっと見つめて言った。
「僕は、信じるよ。」
そして、立ち上がると辺りを見渡して言った。
「ねぇ。綺羅、手伝って。木の実を拾おう。」
綺羅は、何が何だか分からなかったが、言われるままに純と木の実を拾った。純は、綺羅のノートを1枚ちぎると、それに木の実を丁寧に包んで、「メロディーへ」と宛名を書いた。
「ねぇ。綺羅。これは、命の塊だよ。この木の実は、いつか大きな木になっ
てまた実を付けるようになる。メロディーは、この森をいつまでも守らな
きゃいけないんだろう?だから、きっとまた、いつか会える日が来るよ。
きっとさ。今の綺羅の話をメロディーは、どこかで聞いていたと思うよ。
ねぇ。綺羅。綺羅は、その大切な友達の事を、今話してくれたように、全
て書き残して物語にするべきだよ。彼女の存在の全てをね。綺羅には、そ
れをする責任があると思う。そして僕は、綺羅を信じ、守り、愛する責任
があると思う。綺羅の全てを知り、守り、愛したいと思ったのは、間違い
じゃ無かったから・・・・・綺羅を愛しているよ。僕は、綺羅の純粋で素
直な心を愛しているんだ。綺羅の全てが大切で愛おしいんだ。」
純は、そう言うと、綺羅を優しく包むように抱き締めてキスをした。
さて、ここで、物語を終わっても良いんだけど、この物語は、ここでは、まだ、終われないんだ。どうしてかって言うと、続きがあるからなんだよ。当たり前なんだけどね。
それから、数年が経って、二人は結婚した。
綺羅の物語は、認められて本になった。つまり、綺羅は、物語を書く事を仕事にしたんだ。純は、隣町の自動車修理工場で働いている。二人は、綺羅の家で暮らしていた。経緯は色々あるんだけど、面倒臭いから話さないでおくね。あまり、深く聞かないでくれよ。本当に必要の無い事なんだ。それから、また、数年が経って二人の間には、子どもが生まれた。これが、とっても可愛い女の子で名前は、「未来」って言うんだ。えーと読みは、「ミライ」じゃなくて「ミラ」だよ。念の為に言っておくけどね。
未来が5歳になって少し経ったある日、ベットに潜った未来が、綺羅に言った。
「ねぇ。今日もメロディーの話をして!!」
綺羅は、メロディーの話を優しい口調で未来に話していた。未来が突然、思い出したように綺羅に聞いた。
「ねぇ? お母さん。 今でもメロディーが好き? 彼女に会いたい?」
綺羅は言った。
「そうねぇ。お母さんの大切な友達なのよ。メロディーは・・・・・会えな
くなってしまって随分と経つけど、とても大切な友達なの。だから、会え
るなら、会いたいわ。」
未来は言った。
「メロディーも同じ事を言ったわ。ねぇ。お母さん。手を出して。これをお
母さんに渡してってメロディーに言われたの。」
綺羅は、不思議なことを言う娘だと思いながらも手を出した。未来が、綺羅の掌に何かをのせた。
綺羅は、目を疑った。綺羅の掌には、小さな人形用の白いドレスがのっていた。そして、小さな木の実もいくつかのっている。
「少し破れちゃったから、直して持ってきて欲しいって、メロディーが言っ
ていたわ。それから、お母さんの作った物語が聞きたいって・・・・・」
綺羅は、未来の部屋の電気を消すと、溢れては零れる泪を拭った。
未来が、お父さんとお母さんを連れて秘密の花畑に行ったのは、それから間もなくだった。
綺羅は、花畑に寝転がって、物語を書いたノート広げた。未来は、お父さんの手を引いて森を散歩しに行った。
綺羅は、18冊目にノートに綴った物語を読み始めた。綺羅とメロディーの物語だ。まるで、メロディーに読み聞かせるように綺羅は物語を読み進めていった。白いドレスの話に差し掛かった頃、どこからか声がした。
「私のお気に入りのドレスは、どこ? ちゃんと直してくれた?」
綺羅は、辺りを見回してメロディーを探した。彼女は、見当たらない。あちこち見回してみるが、メロディーの姿は見付からなかった。綺羅は、ため息を付くとノートに目を戻した。するとメロディーが、ノートの上で寝転がっていた。
「早く! 早く! 続きは?」
メロディーがせかした。
「私の物語の続きを早く聞かせて!! ずっと待っていたんだよ。
ねぇ。綺羅。早く聞かせて!! そして、私達の物語の続きを書くの。
ねぇ? 綺羅。 良いでしょう?」
綺羅は、メロディーを強く抱き締めると言った。
「もちろんよ。」
メロディーは笑いながら言った。
「だから言ったでしょう? つぶれちゃうって・・・・・・」
さて、この物語は、これでおしまいです。何て言うか、とても乙女チックなお話ですよね。この物語は、前に作った「白い窓」という作品の中で執筆した「妖精の気持ち」という物語に手を加えたものとなっています。文章は、下手ですが、実は結構気に入っている作品の一つでもあります。こういう夢物語のような物語って、歳をとると読まなくなってしまいますよね。現実を沢山知ってしまったというのもあるでしょうし、夢は、所詮、夢。現実は、夢では、生きていけないってのもあるでしょう。ただ、俺は、思うんですよね。仕事柄、子ども達と接していると、純粋で居続けるって事は、大切な事なんだろうなって・・・・・ だから、こういう物語も、恥ずかしがらずに発表しちゃおうって・・・・・ 俺は、いつまでも純粋で居続けたいと思っています。だから、こういう物語も俺の頭から出てきた以上、俺の一部なんだろうなって思います。まぁ、何にせよもう少し、文章や、構成が上手くならないと伝わらないですね。次は、もうちょっと上手く書ける様に頑張ります。最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
稲田大介